平均37.6点(前年比;-9.5点)
問題はこちら→東進ハイスクールさん(解答)
大問1(小問集合)
(1)
9+21÷(-3)
=9-7
=2
(2)
-52×2
=-25×2
=-50
(3)
√24×√5÷√15 ←根号同士で約分
=√8
=2√2
(4)
3a+4-2(a-2)
=3a+4-2a+4
=a+8
(5)
1/3x+1/2y=4 ←6倍
2x+3y=24 …①
5x-3y=18 …②
①+②より、7x=42
x=6
①に代入。y=4
x=6、y=4
(6)
2x2-7x+4=0
解の公式を適用して、x=(7±√17)/4
(7)
反比例の比例定数aは積xy。
a=-2×8=-16
y=-16/x
(9)
全体は6×6=36通り
同数は(1、1)~(6、6)の6通り→同数以外は30通り
大の出目>小の出目、大の出目<小の出目には対称性がある→30÷2=15通り
*たとえば(大、小)=(1、5)(5、1)は裏返しの関係。
確率は15/36=5/12
(10)

具体的な角度が与えられたので、適当なPを描いて角度調査。
△ABPで外角定理→∠BPC=54+36=90°→BP⊥AC
Bを通るACに垂直な線をひき、ACとの交点がP。
大問2(関数)
(1)
ABの傾きは、xの値が-2→3に変化したときの変化の割合である。
y=ax2においてxの値がp→qに変化するときの変化の割合はa(p+q)
1/2(-2+3)=1/2
(2)

各々の座標を確定する。
四角形ACDBは2組の対辺が等しいから平行四辺形。
A→Cは右に1、下に6移動する。
B→Dも右に1、下に6移動して、D(4、-3/2)
(3)

△ABPと平行四辺形ACDBはABが共通辺である。
△ABCが平行四辺形の半分なので、
等積変形の要領で考えるとPはCD上にあればいい。
すなわち、PはCDとy軸の交点になる。
AB//CDより、CDの傾きは1/2
Cから右に1、上に1/2移動して、Pのy座標p=-4+1/2=-7/2
大問3(データの活用)
(1)
範囲=最大値-最小値
=62-42
=20回
(2)
32人の第1四分位数は下位16人の真ん中、下から8番目と9番目の平均。
48と50の平均→49回
(3)

最小値と最大値は同じ。
A組31人の中央値(Q2)は16番目→53回
第1四分位数(Q1)は下から8番目→49回、第3四分位数(Q3)は上から8番目→56回
B組32人のQ2は16番目と17番目の平均→53.5回、Q1は前問の49回
Q3は上から8番目と9番目の平均→56回
B組のQ2(16番目と17番目の平均)を53.5→53回に減らす。

表2のQ2付近をピックアップ。
52以下を消すと18番目…53、17番目&16番目…54だから、Q2を53に減らせない。
→53以降のデータを減らす。Q2が53となるには、大別して以下の2通りがある。
●17番目を52にする。
53を消す必要があるので、訂正例は53→52以下にする(52が繰り上げで17番目になる)
●16番目を53にする。
54以降のデータを53に減らす。
配慮すべきは8番目と9番目の平均であるQ3を変えてはならないこと!
56のセットは崩せないので56以降は不可。54か55を53に変える。
53、54、55
大問4(方程式)
(1)
文字式にする。
a<b
A=2a+5b
B=5a+2b
C=A2-B2
=(A+B)(A-B)
=(2a+5b+5a+2b)(2a+5b-5a-2b)
=(7a+7b)(3b-3a)
=7(a+b)3(b-a)
=21(b+a)(b-a)
a<bより、(b-a)は自然数。
(b+a)(b-a)は整数だから21の倍数になる。
21
(2)

根号を外すには(b+a)(b-a)=21になればいい。
b+a>b-aだから、(b+a、b-a)=(21、1)(7、3)
aとbの和21差1より、和7差3の方がbの値が小さい。
●(7、3)
b+a=7
+)b-a=3
2b =10
b=5
最も小さいbは5
(3)
C=21(b+a)(b-a)=483 ←÷21
(b+a)(b-a)=23
23は素数。23×1=23しかない。
b+a=23 …①
+)b-a=1 …②
2b =24
b=12
②に代入、a=11
a=11、b=12
大問5(空間図形)
(1)
側面積の扇形の面積…母線×半径×π
12×6×π+6×6×π
=108πcm3
(2)①

P、Q、Rは円周を3等分する→弦PQ=QR=RPだから、△PQRは正三角形。
中心をOとする。半径6cmから1辺の長さを調べる。

3辺相等で、△OPQ≡△OQR≡△ORP
∠OQH=60÷2=30°
POを延長、QRとの交点をHとする。対称性から、∠OHQ=90°
(PHは頂角QPRの二等分線で底辺QRを垂直に2等分する)
△OQHの内角から辺の比は1:2:√3→OH=3cm、QH=HR=3√3cm
正三角形PQR=6√3×9÷2=27√3cm2
②

先に円錐の高さを求めておく。
辺の比2:1で三平方→高さは√3だから6√3cm

弧の長さと円周角の大きさは比例する。
弧PQ:弧QR:弧RP=∠PRQ:∠QPR:∠RQP=③:④:⑤
△PRQの内角の和より⑫=180°だから、
∠PRQ=45°、∠QPR=60°、∠RQP=75°

円の中心OからQRに垂線をひき、足をHとする。
半径よりOQ=OR、共通辺OH
斜辺と他の1辺が等しい直角三角形で△OQH≡△ORH
弧QRに対する中心角QOR=60×2=120°→60°ずつに分かれる。
△OQHの内角は30°―60°―90°となり、辺の比は1:2:√3
QH=RH=3√3cm(前問の△OQRと同じ)

今度はQからPRに垂線をひき、交点をIとする。
△QIRは直角二等辺。1:1:√2より、QI=IR=6√3×1/√2=3√6cm
△QIPは1:2:√3の直角三角形。PI=3√6×1/√3=3√2cm
△PQRの面積は底辺PR、高さQIで求まる。
三角錐A―PQRの体積は、(3√2+3√6)×3√6÷2×6√3÷3=54+54√3cm3
大問6(数量変化)
(2)

PがBC上を動くとき、Qは赤線を動く。
y=x×8÷2=4x
(3)

0≦x≦8のとき、底辺と高さが伸びるので、面積はy=ax2に増加する。
x=8のとき、y=8×8÷2=32だから、(x、y)=(8、32)を代入して、
32=64a→a=1/2
y=1/2x2

8≦x≦12のとき、前問よりy=4x
x=12のとき、y=48

大問題は12≦x≦16のとき。
面積は減少し、x=16のとき、y=8(DE)×4÷2=16となるが、
一次関数で減少するのか、y=ax2で減少するのか悩む。
横方向のみの減少なので一次関数で減少する(*詳しくは後述します)

16≦x≦24のとき、面積は減少していき、
x=24のとき、y=0

↑x軸は1マス1秒だが、y軸は2cm2である!
まとめると…
0≦x≦8のとき、y=1/2x2
通過すべき格子点は、原点O→(2、2)→(4、8)→(6、18)→(8、32)
8≦x≦12は(8、32)→(12、48)
12≦x≦16は(12、48)→(16、16)
16≦x≦24は(16、16)→(24、0)
@詳細@
三角形の面積…底辺(横成分)×高さ(縦成分)÷2
横と縦が一定に伸びると、面積はy=ax2で増加。
いずれか一方が一定に伸びると、面積は一次関数(比例)で増加する。
斜めは横成分+縦成分の合成なので、1つの頂点が斜め移動したらy=ax2です。

一直線上に並ぶA・B・Cにおいて、Aが左、Bが右に移動するときの△ABCの経過を追います。
(わかりやすいように、同じ速度で移動するものとします)
ABの中点をDとすると、移動先のABも必ずDを通過します。
錯角と等しい移動距離から一辺両端角相等ゆえ合同→AD=BDになるからです。
△ADA1≡△BDB1のように点対称の関係になります。
DCで三角形を分割します。
△A1DC→△A2DC→△A3DC…は底辺DC、高さの比はA1A、A2A、A3A…
△B1DC→△B2DC→△B3DC…は底辺DC、高さの比はB1B、B2B、B3B…
左右を統合すると、底辺DCは一定、高さの比だけが比例で増加します。
ということは、△ABCの面積は比例で増加することになります。
反対に、AとBが近づけば面積は比例で減少します。
AとBの速さが等しくない場合はDの位置が変わるだけで、同様のことがいえます。
(4)

y=18のラインをひく。
0≦x≦8のとき、(6、18)を通る。x=6
(y=1/2x2にy=18を代入すればいい)
(12、48)→(16、16)
右に4、下に32だから、傾きは-32/4=-8
1秒後に8cm2減少する→過去に遡れば1秒前に8cm2増加。
(16、16)から遡って2cm2増加する時間は、2/8=1/4秒
16-1/4=63/4
x=6、63/4
大問7(平面図形)
(1)
△BEFが二等辺三角形である証明。
角度から攻めるので、2つの底角が等しい点を指摘すればいい。

仮定より、∠BAE=∠CAE=a
接線と半径は垂直だから、∠ABF=90°
△ABFの内角より、∠BFE=180-(a+90)=90-a
@@
(以降が記述部分)
また、半円の弧に対する円周角から∠ACE=90°
△ACEの内角と対頂角より、∠AEC=∠BEF=180-(90+a)=90-a
∠BEF=∠BFEより、2つの底角が等しいので、△BEFは二等辺三角形。
(2)①

弧AC=弧BC→弦AC=弦BC
半円の弧に対する円周角より、∠ACB=90°だから、△ABCは直角二等辺。
∠EAB=45÷2=22.5°

弧BGを求めるには中心角BOGがいる。
これは弧BGに対する中心角なので、∠BOG=22.5×2=45°
弧BGの長さは、2×2×π×45/360=π/2cm
②
難しい(´д`)

∠CAB=45°、∠ABD=90°から、△ABDも直角二等辺。
DB=4cm
求積すべき図形が複雑かつ2ヵ所に分かれているので、分割が使えにくい。
白いエリアも複雑で求めにくい。
取っ掛かりを得るために前問利用をにらむ。
弧BGの曲線部分が面倒。CがOの真上にある点に着目すると…。

OCに補助線。
△ABCは直角二等辺→∠COB=90°
∠COG=90-45=45°
2辺(半径)とあいだの角が等しく、二等辺OBG≡二等辺OCG
弧と弦に囲まれた部分(中心角45°の扇形-二等辺)を移植する。

さらに、もう1ヵ所を集められないか。
半円の弧に対する円周角より、∠AGB=90°
二等辺BEFとBG⊥EFから、斜辺と他の1辺が等しい直角三角形で△BEG≡△BFG
右側に移植する。

まとめると上図のようになる。
GからOBに垂線、足をHとする。
△OGHは直角二等辺→1:1:√2より、GH=√2cm
求積すべき図形は、直角二等辺ABD-(△AOC+△OBG×2)
=4×4÷2-(2×2÷2+2×√2÷2×2)
=6-2√2cm2
●講評●
大問7編成で厳しい設問がいくつもある。
大問数を1つ減らしても厳しいラインナップだと思う。
ゆとりがある人以外、難問には付き合わない方が良い。
大問1
ここでできるだけ稼いでおきたい。
(10)想定したPをもとに角度を調査して方針を立てる。
大問2
(2)までは取りたい。公立入試で座標平面上の平行四辺形は頻出。
(3)平行四辺形であることを掴み、これの半分となる三角形を考える。
平行四辺形を対角線で割ると2等分される。等積変形で頂点をy軸上に移す。
大問3
(3)やや重いので後回ししてもいい。
一応、1行16個で整理されているので、中央値を判断しやすくしてあるが、
A組B組のQ1~Q3を調べるのに参ってしまった人はいたはず。
Q2の両サイドの一方をどう変えるか。論理的思考力が厳しく問われる。
数値の並びから52以下はいじれない。上をいじるとなると、Q3を崩さないよう気を配る。
大問4
(1)から飛ばし過ぎ。
ここを間違えるとドミノ式で×なので、全滅した生徒は少なくないだろう。
足し算は項を入れ替えても問題ないから(交換法則)、(b+a)にしておくと次が対処しやすい。
(2)2通りでてくるので(3)よりやりづらさはあるかも。
和21差1は半分の10.5の両サイド→10と11。和7パターンの方がbの値は小さい。
大問5
(1)円錐の側面積は公式で対処したい。なぜそうなるのかも押さえておきたい。
(2)本番では対称性を使って次々に角度認定していくのがいい。
(3)ここも正答率は低いだろう。
45°―60°―75°の三角形を2種類の有名三角形に分割する。経験差が出やすい。
2025年青森大問5に類題が出ている(三角形の1辺を求める…11.3%、三角形の面積を求める…0.2%)
富山は弧の長さの比より内角を求める作業からスタートし、
小問の小刻みなしに三角錐の体積まで要求された。
大問6
(2)までは取りたい。
(3)12≦x≦16をどう対処するか…。
原点以外の放物線は公立入試では見かけないので、一次関数にはってしまうのも手かも。。
直線であれば始点と終点の座標を確定するだけで引ける。
0≦x≦8は途中で通過すべき格子点が3点ある。
(4)内容は他県でも見かけるものだが、難問を飛ばしていないと時間不足に陥る。
大問7
(2)①中心角BOGをどう求めるか。45°を半分→2倍で45°
②難問。正答者ゼロでは?
球積すべき図形で最も厄介なポイントは弧BG。
前問で中心角BOGを使ったので、∠COG=45°に目を向けられたら、
曲線部分をBG→CGにあてはめることができる。
さらに分離した△BEGは(1)の二等辺+∠BGE=90°で移植できる。
失点しても合否に影響はないので他を取ろう。



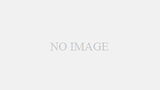
コメント