平均57.5点(前年比;+6.5点)

問題PDF
大問1(物理総合)
(ア)4 39.8%

*側面Aに対する垂線(法線)とのあいだの角が入射角。
プリズムを反時計回りすると、青線の十字も反時計回りする。
光源装置から出る光は動かないから、側面Aでの入射角は小さくなる。

理科便覧ネットワークより。
水面に対して垂直に光が入射すると、光は屈折せずに直進する。
ここから光の向きを少しずつ右側に傾ける。
水から空気に出るとき、〔入射角<屈折角〕
a→b→cと入射角を大きくすると、cで屈折角が90°になり、光が水から出なくなる。
cの角度を臨界角という。臨界角を超えると光が全反射する。
側面Bで全反射が起きた→側面Bでの入射角は大きくなった。
@余談@
臨界角の大きさは、光が何の物質から何の物質を通ったかで決まる。
水→空気の臨界角は約49°、石英ガラス→空気は約43°
石英ガラスは光ファイバーに用いられるガラスである。
光ファイバーは光信号を全反射させることで、高速かつ長距離の情報伝達を可能にする。
(イ)3 37.4%

*X:テコに置き換えるとわかりやすい。
車軸を支点とすると、支点からの距離は②:⑤
重さは逆比で⑤:②
手が引っ張る力は、20×②/⑤=8N

Y:小さい円と大きい円の半径の比は2:5
→直径の比も2:5→円周率をかけた円周の比も2:5
2つの円は同時に回転するので、ある角度を回したときの弧の長さも②:⑤
手で⑤の長さを引っ張ると、おもりは②上がる。
ひもを引く長さは、30×⑤/②=75cm
Z:仕事(J)=力(N)×距離(m)
おもりの上昇…20N×0.3m=6.0N
手が引っ張る…8N×0.75m=6.0N
仕事の原理から道具を使っても仕事の大きさは変わらない。
(ウ)ⅰ 1 66.9%

*2人の体重の和は変わらない。
?=(57.5+52.5)-55.0=55.0kg
ⅱ 1 53.0%
*AがBの肩に手を乗せた→Aの体重の一部がB側に移ったことで、
Aの体重計は-2.5kg、Bの体重計は+2.5kgになった。
『BがAから受ける下向きの力』を作用とすると、反作用は『AがBから受ける上向きの力』
この上向きの力は2.5kg=2500g=25N
大問2(化学総合)
(ア)2 64.5%

溶解度…水100gに溶ける物質の最大量。
最初の80℃ではAとBすべてが溶けている。
Aが120g溶ける温度は63℃くらい。これより下だと一部が結晶になる。
Bが30g溶ける温度は43℃くらい。これより下だと一部が結晶になる。
Aだけ結晶になる温度はこの間なので、選択肢では50℃。
(イ)4 75.3%

*右辺にある元素を消し、左辺に残った元素の組み合わせを選ぶ。
@@
炭酸水素ナトリウムの熱分解の化学反応式
2NaHCO3(炭酸水素ナトリウム)→Na2CO3(炭酸ナトリウム)+CO2+H2O
(ウ)ⅰ 2 72.5%
ⅱ 1 73.2%
*ダニエル電池。
イオン化傾向(イオンへのなりやすさ)の大きい亜鉛が先にイオン化(電離)する。
亜鉛(Zn)が2個の電子を放出して亜鉛イオン(Zn2+)になる。
Zn→Zn2++2e-(eは電子)
亜鉛イオンは溶液へ(亜鉛の質量は減少)
電子が亜鉛板から導線を伝って銅板に流れ、電流が生まれる。
電流の向きは電子の流れの逆だから、電流は【銅板→亜鉛板】
銅板側では硫酸銅水溶液が以下のように電離している。
CuSO4(硫酸銅)→Cu2+(銅イオン)+SO42-(硫酸イオン)
銅イオンが銅板から2個の電子を受け取って、銅板に銅Cuが析出する。(銅の質量は増加)
Cu2++2e-→Cu
大問3(生物総合)
(ア)4 71.2%
*1:アブラナもマツも種子で増える種子植物。
種子植物から被子植物(胚珠が子房に包まれる)と裸子植物(胚珠が剥き出し)に分かれる。
アブラナは被子植物、マツは裸子植物。
2:アブラナはめしべ1本、おしべ6本、花弁とがくがそれぞれ4枚ある。

風媒花のマツの花は、虫媒花のアブラナのように虫をおびき寄せる必要がないため、
鮮やかな花弁がなく、がくもない。先端に雌花、その下に雄花がある。
雌花に剥き出しの胚珠があり、雄花の花粉のうで花粉が作られる。
雌花に受粉してから種子ができるまで1年半~2年ほどかかる。
3:子房が果実になる。子房の中にある胚珠が種子になる。
マツには子房がないので果実はならない。
@余談@
裸子植物は風媒花が多いが、ソテツの一部は受粉に動物を使うようです。
(イ)7 73.7%

*hi-hoより、動物細胞と植物細胞。
●核
核膜に覆われる核の中に染色体があり、
染色体のDNA(デオキシリボ核酸)に生物の設計図である遺伝子が刻まれている。
染色体の名前の由来は、酢酸カーミンや酢酸オルセインで赤く染まることから。
真核生物は核膜で区切られた核をもち、原核生物は核膜がなく、核がはっきりしていない。
●葉緑体
光合成をする場所。葉緑素(クロロフィル)という緑色の色素をもつ。
神奈川の過去問で出題されたと思うが、すべての植物の細胞に葉緑体があるわけではない。
太陽光の届かない地中にある根の細胞は緑色ではなく、葉緑体がない。
●細胞膜
いずれの細胞にもある。
細胞膜は一定以上の大きい分子を通さない半透膜の性質をもつ。
●細胞壁
植物細胞のみ。菌類や細菌類にもある。植物での主成分はセルロースで硬い。
細胞を強固に守る反面、細胞を自由に動かすことができない。
●液胞
問題では光学顕微鏡で観察できた植物細胞のみとなっているが、
電子顕微鏡でみると動物細胞にもわずかに液胞のようなものが存在する。
液胞は老廃物の貯蔵や水分の調節などをする細胞小器官で、植物細胞で大きく発達している。
(ウ)1 64.5%

*(A・C)と(B・D)は指示薬が違うだけで中身が同じ。
対照実験では調べたい条件以外の条件を等しくする。
→調べたい条件は変えなくてはならない。
また、結果を比較するので同じ指示薬を使った試験管を比べる。
(A・B)…Bはデンプンのままだが、Aはデンプンがない⇒唾液でデンプンで消えた。
(C・D)…Cは糖があるが、Dにはない⇒唾液で糖があらわれた。
まとめると、唾液(消化酵素;アミラーゼ)によりデンプンが糖に変わった。
大問4(地学総合)
(ア)3 39.8%

*まずは地層の新旧を判定する。
堆積岩は粒子の大きい順(礫>砂>泥)に堆積する。
拡大図では内側の粒子が大きいので、図1よりd→c→b→aの順で堆積した。

褶曲した地層をもとの平らな地層に戻したとき、内側が下に来るのは図2。
(イ)4 48.5%

*a:金星は地球の軌道より内側を周回する内惑星。
地球の真夜中では反対方向(地平線の下)にあって見えない。×
明け方の東の空に明けの明星、夕方の西の空に宵の明星として観測できる。
b:火星は地球の軌道より外側を周回する外惑星。
真夜中に火星は観測できる。〇
c:地球から見ると満月→地球を挟んで月と太陽が反対方向にある。【月―地球―太陽】
月食は地球が月と太陽のあいだに入ることで、月に影ができる現象。×
d:地球からみると新月→月の先に太陽がある。【地球―月―太陽】
日食は月が太陽と地球のあいだに入ることで、太陽が隠れて見える現象。〇
(ウ)X 3 56.0%

*太陽光がパネルに対して垂直に当たるとき、発電効率は最も高くなる。
太陽光を延長した直線と地面がなす角が太陽高度。
外角定理より、90-33=57°
Y 2 67.3%
*前図の外角定理より、【パネルの角度+太陽高度=90°】
神奈川より沖縄は緯度が低く、赤道に近い→太陽高度が大きい。
太陽高度が大きいからパネルの角度は小さくなる。
@ペロブスカイト太陽電池@

TELESCOPE magagineより。次世代型太陽電池、通称・曲がる太陽電池!
フィルム状ゆえ従来のシリコン素材より軽量。厚さはなんと1マイクロメートル(0.001mm)!表面を保護する物質を被覆しても0.2mm以下に抑えられる超薄型太陽電池だ。ペロブスカイトの名はもとはロシア人の鉱物学者ペロフスキーから由来するそうで、NH3CH3PbI3という化学式で表される特殊な結晶構造・ペロブスカイト構造を利用する。
湾曲しても壊れない柔軟性に富み、屋上だけではなく壁面にも貼り付けられるので、電柱や自動車、衣服などあらゆるものが発電場所の対象となり、国土面積の狭い我が国では設置場所の制約を大幅に取り払える。製造面でも比較的容易な工程から得られ、主原料のヨウ素は自国で調達できるから国内での大量生産が見込まれている(日本はヨウ素生産量2位、産出地の多くは千葉である)
発電効率は改良を重ねて従来のシリコン製に迫る勢いで、電灯や蛍光灯の弱い光でも発電できることからリモコンやスマホの充電にも使用可能!各企業や家庭で普及が進めばエネルギー自給率が高まるので、経済安全保障の観点からも期待されている技術である。一方、現況のペロブスカイト太陽電池は耐久性に難があり、寿命が短い課題をもつ。また、少量ながらも環境負荷の高い鉛(Pb)が含まれている点も気がかりだ。日本政府は次世代型太陽電池の普及拡大に向け、様々な支援策を講じている。
大問5(電磁気・音)
(ア)3 44.9%

*X:表の電流0mAから、コイルの重さは10.8g
電流を流すとコイルに磁界が発生。磁石の磁界と及ぼし合い、コイルが力を受ける。
電流を大きくすると、てんびんの値が大きくなる→コイルに下向きの力(イ)がかかる。
Y:磁石の下側がN極。
コイルに下向きの力をかけるには、N極同士で反発させる。
コイルの上側がN極だから、コイルの内側は上向きの磁界(ア)がつくられる。
@@
右ねじの法則より、上からみてコイルの電流は反時計回りに流れている。
(イ)2 24.6%!

*電流の向きを逆にすると、コイルの内側の磁界の向きが下に変わる。
コイルの上側がS極になり、コイルが磁石に引き寄せられる。
→コイルに上向きの力がかかるので、てんびんの値は小さくなる(軽くなる)
先ほどは100mAで下向きに、12.48-10.8=1.68gの力がかかっていた。
今度は上向きに1.68gかかるから、10.8-1.68=9.12g
(ウ)4 40.3%

*交流電流は一定の周期で電流の向きや大きさが変化する。
(周波数が50Hzの東日本では1秒間に50回、60Hzの西日本では60回変わる)
発光ダイオード(LED)は足が長い方が+、短い方が-で+→-のみ電流が流れる。
電流が時計回りだと上、反時計回りだと下のLEDが光り、棒を振ると交互に点灯する。
ちなみに、LEDを接続するときは必ず抵抗器もつけておく。
規定以上の電流が流れないようにするなど、いくつか理由があるようです。

直流は電流の向きや大きさが一定。
電池の長い方が+だから時計回りに電流が流れる→上のLEDだけが点灯しつづける。
(エ)2 48.2%

図4→図9の波形の変化をみると、
●振幅が大きくなる→音が大きくなる。
電圧を大きくしてコイルに大きな電流を流す。
コイルの磁界が強くなり、コップの底が大きく振動して音が大きくなる(音は分子(空気)の振動)
●波長が長くなる→音が低くなる。
周波数(振動数)…1秒あたりに通過する波の数
周波数と波長は反比例(波長=波の速さ÷周波数;波の速さは一定)
周波数を小さくすれば1秒あたりのコップの底の振動数が減り、波長が長くなる。
大問6(イオン)
(ア)1 84.2%
*イオンが電子を受け渡しすることで水溶液に電流が流れる。
水に溶けて電離し、水溶液に電流が流れる物質を電解質という。
水に溶けても電離せず、水溶液に電流が流れない物質を非電解質という。
砂糖と同じ非電解質はエタノール。
@@
化学式は以下の通り。
CuCl2(塩化銅)→Cu2+(銅イオン)+2Cl-(塩化物イオン)
H2SO4(硫酸)→2H+(水素イオン)+SO42-(硫酸イオン)
KNO3(硝酸カリウム)→K+(カリウムイオン)+NO3-(硝酸イオン)
(イ)5 65.3%
*塩酸の電気分解。
HCl(塩酸)→H++Cl-
陽極に陰イオンのCl-が集まり、電子を放出して塩素Cl2が発生。
〔2Cl-→Cl2+2e-〕
陰極に陽イオンのH+が集まり、電子を受け取って水素H2が発生。
〔2H++2e-→H2〕
化学反応式…2HCl→H2+Cl2
(ウ)3 62.2%
*Ba(OH)2(水酸化バリウム)→Ba2+(バリウムイオン)+2OH-(水酸化物イオン)
H2SO4(硫酸)→2H++SO42-(硫酸イオン)
水酸化バリウム水溶液に硫酸を加えると、中和反応で2OH-+2H+→2H2O(水)ができる。
また、塩としてBa2++SO42-→BaSO4(硫酸バリウム)ができる。
硫酸バリウムは水に溶けず、沈殿する。

経過を追う。
最初はBa2+とOH-(数量比は係数から1:2)
中和点CまでOH-はH+と中和して減少、H+は0のまま。
Ba2+もSO42-と反応して減少、SO42-も0のまま。BaSO4の沈殿は増える。
中和点を過ぎると、OH-とBa2+は枯渇して0。材料のBa2+がないからBaSO4も増えなくなる。
硫酸だけが増えるので、H+とSO42-が増加(数量比は係数から2:1)

Dは中和点後だから、H+とSO42-が余る。
(エ)あ 4 69.9%
*点Cは電流0mA→イオンがほぼ無かったため、電流が流れなかった。
中和点だから水H2Oと塩化バリウムBaSO4のみ。
水はわずかに電離する(H2O→H++OH-)ので、イオンが”ほぼ無い”。
い 2 57.0%
*HCl(塩酸)+NaOH(水酸化ナトリウム)→NaCl(塩化ナトリウム)+H2O
塩である塩化ナトリウムは電解質である。
NaOH→Na++OH-
中和反応で生成した塩が電離して水溶液中にイオンがあるから、中和点でも電流が流れた。
う 3 42.4%

*中和点Fでは50mAの電流が流れた→50mAを流すほどのイオンの量がある。
グラフ1より、塩化ナトリウム水溶液の50mAのときの質量パーセント濃度は4%。
大問7(遺伝)
(ア)4 85.0%

*精子・卵といった生殖細胞は、減数分裂で染色体の数が半分になる。
受精してもとの染色体の数に戻る。
また、色と長さに関する遺伝子はそれぞれ独立して遺伝する(独立の法則)
(イ)3 71.4%

*顕性は黒(A)、潜性は茶(a)
③親が純系の黒(AA)×純系の茶(aa)の交配。
子はすべてAaで黒。
⑤親が黒(Aa)×黒(Aa)の交配。
1:③遺伝子の組み合わせはAaの1通り。
2:③茶の遺伝子aを皆受け継いでいる。
潜性遺伝子aは消えたわけではなく、分離の法則で別々の生殖細胞に入る。
3:⑤孫世代の4つのうち、2つがAa。〇
4:⑤黒:茶=3:1
(ウ)1 80.2%
*Yは潜性の茶色だから【aa】が確定。
黒のXは【AA】か【Aa】のいずれか。

左表がX【AA】、右表がX【Aa】の場合。
1:茶色ができるのは右表。Xは【Aa】となる。〇
2:Xが【AA】だと子は全部黒になる。×
3:黒のみは左図の【AA】×
4:茶のみは【aa】×【aa】の交配しかない。×
(エ)あ 2 73.4%
*【AABB】×【aabb】の交配。色と長さで区別する。
色は【AA】×【aa】、前図よりすべて【Aa】で黒。
長さは【BB】×【bb】、同様にすべて【Bb】で短い。
すべて【AaBb】だから黒で短い。
い 4 30.2%!

*表を埋める。
色…顕性Aを含めば黒。aaのみ茶。
長さ…顕性Bを含めば短い。bbのみ長い。
(黒短):(茶長)=9:1
@余談@
(黒短):(黒長):(茶短):(茶長)=9:3:3:1
色だけで見ると、黒:茶=12:4=3:1
長さだけ見ると、短:長=12:4=3:1
↑前問の孫世代の3:1と同じ。
ちなみに、次の世代は(黒短):(黒長):(茶短):(茶長)=25:15:15:9
黒:茶=短:長=40:24=5:3になる。
大問8(気象)
(ア)1 54.0%

*温帯低気圧は暖気と寒気がぶつかりやすい温帯で発生する低気圧。
台風(熱帯低気圧)が弱まることでも起こる。
前線Bは寒気優勢の寒冷前線。前線Aは暖気優勢の温暖前線。

寒気は暖気より密度が大きく、暖気の下に沈む。
雲の形に注目しよう!
●寒冷前線では寒気が暖気の下を潜り込みながら進む→寒気が暖気を押し上げる。
縦長の雲(積乱雲)が発生し、狭い範囲に強い雨をもたらす。
●温暖前線では暖気が寒気の上を滑り込むように進む→暖気が寒気の上をはい上がる。
横に広い雲が発生し、広範囲に弱い雨をもたらす。
(イ)1 34.2%

*湿度=(空気1m3あたりの水蒸気量)/(その気温の飽和水蒸気量)×100
飽和水蒸気量…空気1m3に溶け込める空気の最大量(g)
飽和水蒸気量に対して実際に空気に溶けている水蒸気量の割合が湿度。
本問は温度と飽和水蒸気量の関係を示すグラフが与えられていない。
飽和水蒸気量は温度が高いほど大きくなる。
アは気温が最も高いので、飽和水蒸気量が最も大きい(空気に多くの水蒸気が溶けている)
湿度も最も高いから、水蒸気量が最も多い。
イとウは湿度が同程度で、気温はイの方が高い。
イの方が飽和水蒸気量が多いから水蒸気量も多い。
1m3あたりの水蒸気量は多い順にア>イ>ウ
(ウ)3 58.8%

*雨が降っていた→湿度が100%に近いのは3ヵ所。
最初は温暖前線が横浜を通過する。寒気→暖気だから気温は急上昇する。
その後、寒冷前線が横浜を通過する。暖気→寒気だから気温は急降下する。

風向が変わる点も大きなポイントである。
1日目12時;北寄り→南寄りの風
2日目10時;南寄り→北寄りの風
(エ)2 47.2%

*2日目2時も4時も似た風向なので、わかりやすい2時の風向で考える。
熊本だけ北寄りの風→熊本はまだ寒冷前線を通過していない。

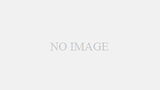
コメント