問題PDF
地球上にいるほとんどの動物や植物は、約24時間のサイクル(概日リズム)で活動しています。例えば、昼間、洞窟の奥にいるコウモリは、夕方の適切な時刻に洞窟から出て行くことができます。このように、生物に時間を知らせるシステムを体内時計といいます。体内時計の存在が初めて報告されたのは、①マメ科植物のオジギソウという植物です。18世紀、フランスの天文学者が②オジギソウの葉が昼間に開き、夜に葉を閉じ、枝(葉柄)を垂らす現象(就眠運動)に注目しました。太陽の光の影響で就眠運動はおこると考えられていましたが、オジギソウを暗室に持っていくと、暗闇の中でも、昼間に葉を開き、夜に葉を閉じるなど就眠運動はおこり、それが何日もくりかえされました。そこで、オジギソウ自身の中に体内時計があると考えられるようになりました。
1984年、ショウジョウバエを使って、体内時計をつかさどる「時計遺伝子」や「時計タンパク質」が発見されました。後に、これらのはたらくしくみはヒトを含む多くの生物と共通していることが明らかにされました。この功績から、2017年、アメリカの研究者3人に③ノーベル生理学医学賞が贈られました。
(1)
下線部①のマメ科植物であるインゲンマメについて、
水にひたした種子の断面図を表した模式図を選びなさい。

(2)
下線部②について、オジギソウは葉などに触れると就眠運動とほぼ同様に葉を閉じ葉柄が垂れていきます(図1)。葉柄の付け根部分は、他の茎の表面部分と比べると柔らかく、関節のような役割をしており、この部分を「葉枕」といいます。図2は、その「葉枕」の断面を模式的に示したものです。葉枕を構成している細胞を上側と下側とに分けています。

①
葉枕の上部と下部の細胞に、はじめ均等に存在していた水が移動することで葉柄は垂れます。
そのときの水の移動方向を図2のA、Bから選びなさい。
②
葉枕の上部と下部の細胞の大きさに触れながら、葉柄が垂れるしくみを簡潔に答えなさい。
(3)
下線部③について、2018年のノーベル生理学医学賞は日本人が受賞しました。
その人の名前を選びなさい。
ア:利根川進 イ:山中伸弥 ウ:大村智 エ:本庶佑
(4)
体内時計に関して、次の実験を行いました。
【実験】
温度や湿度などが一定に保たれた条件で、6時に点灯し、18時に消灯するように、1日のうち12時間は明るくして明暗のサイクルをつくった。このサイクルでマウスを5日間飼育し、その後、6日目の6時に点灯せず、以後は一日中完全に暗くした。その間の、図3のようなマウスの輪回し行動などの活動量を記録した。

【結果】
図4は、横軸を12時から始まる時刻、縦軸を観察日数とし、観察日数ごとに活動の見られた時間帯に活動量を太線で表したものである。また、明るくしている時間帯(明期)は白、暗くしている時間帯(暗期)は灰色の背景で示した、明期、暗期が12時間ずつの24時間サイクルでは、マウスは暗期にだけ活動し、夜行性であることが分かった。7日目からは活動している時間の長さは変わらずに、10日間かけて活動開始時刻が18時から14時まで移動していた。

①
マウスと同じ夜行性の動物を3つ選びなさい。

②
図4の7日目以降の結果から、マウスの概日リズムは何時間何分か計算しなさい。
③
図4の1日目から5日目では、ある刺激によってマウスの体内時計が調整され、マウスは明期、暗期が12時間ずつの24時間のサイクルに合わせて活動しています。マウスの体内時計はどんな刺激によって、どのように調整されているのですか。簡潔に説明しなさい。
@解説@
(1)ア

ア:インゲンマメ イ:トウモロコシ ウ:カキ エ:イネ
(2)①A
②葉枕の下部の細胞が縮み、葉の重さで垂れる。
*筋肉のないオジギソウが垂れる仕組み。
オジギソウの葉柄の付け根には葉枕があり、葉枕は上部と下部の2層に別れている。
葉枕の上部細胞に水が移動することで下部細胞が収縮し、葉の重みで下に垂れる。
(植物細胞は膨圧という、細胞の外側をおおう細胞壁を内側から押す圧力が働いており、
オジギソウが垂れる主な原因は膨圧の変化だそうです)
(3)エ
どの方もノーベル生理医学賞の受賞者だが、有名な時事なので取りやすい。
利根川進…1987年。ヒトの免疫システムの仕組みを遺伝子から解き明かした。
山中伸弥…2012年。万能細胞の一種、iPS細胞の開発者。
大村智…2015年。イベルメクチンという熱帯に住む寄生虫由来の病原治療薬の発明。
本庶佑…2018年。ガンの新治療薬オプジーボの開発。
(4)①ア・ウ・エ
ア:カブトムシ、ウ:コアラ、エ:ムササビ
イ:ハト、オ:リスは昼行性。
②23時間36分
概日リズムは1日のサイクル。
夜行性であるマウスの活動開始時刻が18時から14時と4時間早くなっている。
10日間で4時間早くなるので、1日あたりでは4×60÷10=24分ずつ早くなる。
1日の概日リズムは、24時間-24分=23時間36分
③光の刺激によって、1日のリズムを24時間周期に戻す。
*実験では光の有無しかないので、刺激の中身は光しかない。
人間も太陽の光を適度に浴びないと、概日リズムが狂って睡眠障害をきたす。

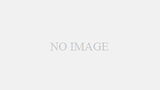
コメント