問題PDF
下の文1・文2を読んで、あとの問いに答えなさい。
〔文1〕
氷河は固体の状態ですが、水のように少しずつ移動しています。
そのため、水と同様に周囲を侵食したり、物質を運搬したりする作用があります。
また、氷河がとけると、それまで氷河により運搬されていた岩石が氷河から落下し、
堆積する作用もあります。氷河の作用により堆積したものは氷成堆積物と呼ばれています。
氷河は存在する地域では、氷河の浸食作用によりスプーンで削ったように地面が侵食され、
ホルン(下の写真)や( )とよばれる地形が形成されます。
日本にも過去に形成されたホルンが存在しています。

(1)文中の( )に入る語句として適切なものを選びなさい。
ア:V字谷 イ:U字谷 ウ:Y字谷 エ:T字谷
(2)
氷河の両側や先端にも、氷成堆積物があります。
これらの堆積物の特徴として、最も適切なものを選びなさい。
ア:角が丸くなっており、粒の大きさがそろっている。
イ:角張っているものがあり、粒の大きさがそろっている。
ウ:角が丸くなっており、粒の大きさが不ぞろいである。
エ:角張っているものがあり、粒の大きさが不ぞろいである。
(3)
下線部の事実から、ホルンが形成された当時の日本の気候について
予測できることを述べなさい。
〔文2〕
約23億年前と約7億年前には、地球は赤道付近や海洋まで氷河に覆われ、
真っ白な地球になり、この状態が長く続いたと考えられています。
この状態は全球凍結と呼ばれています。
①いったん全球凍結の状態になると、この状態が長く続きやすくなると考えられています。
②大陸から離れた海洋の層から氷成堆積物が発見されたことが、
この全球凍結の証拠の1つとされています。
(4)下線部①に関して、全球凍結の状態が長く続きやすくなる理由として
最も適切なものを選びなさい。
ア:氷ができることによって冬の期間が長くなり、夜の時間が長くなったから。
イ:日食の回数が多くなったため、太陽光が当たる時間が少なくなったから。
ウ:氷が地球全体で形成されたため、海水の塩分濃度が上がり、氷が溶けにくくなったから。
エ:氷河は鏡のように光を反射してしまうから。
オ:生物の活動が少なくなるので、大気への二酸化炭素の排出量が減ってしまうから。
カ:地球内部まで冷やされることにより、火山活動が止まってしまうから。
(5)
全球凍結の証拠としては下線部②の情報だけでは不十分です。
この地層が堆積した場所の情報を、他にも読み取る必要があります。
どのような情報が必要なのか、選びなさい。
ア:地層が堆積した当時の海水の温度 イ:地層が堆積した当時の緯度
ウ:地層が堆積した当時の経度 エ:地層が堆積した当時の塩分濃度
(6)
図1に、2地点の地層を示します。
この2地点には同じ時代の全球凍結を記録した層が含まれます。
炭酸塩岩は、塩酸をかけると二酸化炭素が発生する岩石です。
地点Bの地層には、マンガンや鉄などの金属を多く含む層がみられます。
図1を見て、この2地点の地層からわかることとして、最も適切なものを選びなさい。
地層の上下の逆転はないものとします。また、層の厚さは実際の厚さを反映していません。

ア:全球凍結の状態が終わった原因は、火山の大噴火で流れ出した溶岩が世界中をおおったからである。
イ:全球凍結の状態になった原因は、大気中の二酸化炭素が大量に減少したからである。
ウ:全球凍結の状態が終わった後、大気中には二酸化炭素が大量に存在した。
エ:全球凍結の状態になると、世界中の海洋で鉄分の濃度が増大した。
オ:全球凍結の状態になった原因は、生物が繁栄したからである。
@解説@
(1)イ
河川のV字谷、氷河のU字谷。
氷は固体だが、巨大な氷河は重力に従ってゆっくりと動いている。
谷をU字に削り取るほど大きな浸食作用が働く。
(2)エ
河川と対比して考えるとわかりやすい。
川の石は流れている最中に石同士がゴツゴツとぶつかるので丸みを帯びるが、
氷河の場合は氷の上や中に閉じ込められながら運搬されるので、
ゴツゴツとぶつからず、堆積物は角張っており、粒の大きさは不ぞろい。
ちなみに、氷河に運搬された土砂が積もった丘状の地形をモレーンという。
(3)氷河ができるほど気温が低かった。
ホルンとは氷河の侵食を受けて、周りが削られたことでとがった山頂。
ホルンがあったということは日本にも氷河があった→氷河ができるほど寒かった。

日本で氷河が見られるのは北海道…ではなく、富山の立山連峰。
規模は小さいので、U字谷の形成は難しいか。
氷期では日高山脈や飛騨山脈にも山岳氷河があったようだ。
(4)エ
全球凍結は授業で習わないので推測するしかない。
全球凍結が長く続くということは、地球が温かくならないから。
選択肢のなかでありえそうなのは、エの氷河の反射。
太陽光を反射してしまえば、地球に熱が吸収されにくくなる。
氷河による太陽光の反射は地球温暖化の話でも登場する。
極地方の氷河は太陽光を強く反射しており、太陽からの放射エネルギーを抑えている。
温暖化によって氷が溶けると、光を反射する氷河の表面積が減ってしまうので、
地球の温暖化はより進行してしまう。
さらに、氷のなかに眠っていたメタン(温室効果ガスの一種)が放出されて温暖化を促進する。
このように温暖化は加速していく!
@温室効果ガス@
京都議定書やパリ協定で規制される温室効果ガスといえば二酸化炭素やメタンが挙げられるが、
地球を最も温めているガスは水蒸気である。
しかし、水の惑星である地球において水蒸気は自然に発生するもので、
人為的に作り出したガスではないから規制対象にはならない(そもそも規制のしようがない)
正答は「いったん全球凍結ができると凍結が長く続く理由」
“一度地球が凍ること”が前提にこないものは誤答となる。
ア:四季ができるのは公転面に対する垂線より自転軸が傾く状態で、地球が太陽の周りを公転しているから。
地球の位置によって昼夜の時間や南中高度が変わってくる。
イ:日食は月が太陽と地球のあいだに入り、3つの天体が一直線上に並んだときに起こる。
ウ:食塩をいれると氷水の水温は低くなるが、同時に凝固点(液体→固体の温度)も下がる。
水は0℃で氷に状態変化するが、食塩を溶かすとある程度マイナスの温度でも水の状態を維持できる。
逆にいえば、凝固点の降下により氷点下で氷→水に融解するので、むしろ氷河は溶けやすくなる。
オ:二酸化炭素は温室効果ガスに含まれるのは、太陽から熱を受けた地球が宇宙に熱を放出する際に、
熱を吸収したり地表に返すから。現代の二酸化炭素の増加は化石燃料(石油・石炭・天然ガス)の燃焼と、
森林の伐採による。生物の呼吸による排出量は割合としてかなり少ない。
カ:確かに地球内部まで冷えてしまったら氷を溶かしにくいように思えるが、
地球内部からジワジワ伝わる地熱より、太陽の莫大な放射エネルギーの方が地表面をまんべんなく温める。
地表や海底に火山活動が盛んな場所もあったと思うが、全球レベルの凍結を溶かすとなると、
やはり地球の半球を常に照らし続ける太陽の光が大きく関係する。
(夏の猛暑←→冬の極寒の気温差も太陽光の影響差)
リード文でも『真っ白な地球になり、この状態が長く続いたと考えられています』とあるので、地球の見た目(白)をきっかけに、なんとか太陽光の反射に思考を飛ばしたい。
ちなみに、全休凍結からの脱却は、火山活動による大気中の温室効果ガスの濃度上昇によって温暖化が進み、氷が溶けたといわれている。
(5)イ
『大陸から離れた海洋の層から氷成堆積物が発見された』ら、冷めやすい大陸だけでなく、海も凍っていたと考えられる。問題はその地層が当時そこにあったか。ウェゲナーの大陸移動説のとおり、地殻変動によって大陸(地層)が高緯度から移動してきた可能性がある。全球凍結を示すには、気温の高い赤道付近(低緯度)でも凍っていた点まで言及しなければならない。よって、”地層が堆積した当時の緯度”の情報が求められる。
(6)ウ
2地点がどこにあるかわかっていない(ものすごく離れているかもしれない)
『同じ時代の全球凍結を記録した層』とあるので、
一番下の『氷成堆積物を含む海洋の層』は共通の地層である。
地層の上下の逆転はなく、その上に乗っかっている地層から判断するので、
全球凍結が終わった後の時代、すなわち、アかウに絞られる。
いろいろ紛らわしくしているが、地点Aと地点Bの情報は図1しかないので、
図1から判断できることはABで共通する炭酸塩岩の地層しかない→ウ
炭酸塩岩の一種が石灰岩。
石灰に塩酸をかけると二酸化炭素が発生する。
一部の生物が光合成などで大気中の二酸化炭素を炭素固定すると、
炭素を含む化合物(有機化合物)として生物に利用されるようになる。
大気のCO2が生体に組み込まれ、生物が死んで堆積すると石灰岩のような炭酸塩岩ができる。
炭酸固定は高校生物で習う。
炭酸塩岩が石灰岩であると推測し、生物の死骸が堆積した地層
→二酸化炭素絡み?と判断するしかないような。
@メモ@
全球凍結について、いろいろ調べてみました。
2度の全球凍結は、なんと生物の進化において重要な転換点となった可能性があるようです!
サイエンスあれこれさんより。
古い方の全球凍結は原核生物から真核生物(細胞核のある生物)の誕生、
新しい方の全球凍結は単細胞生物から多細胞生物の誕生時期とかぶるのだとか。
どうやら酸素濃度の上昇が関連しているそうで、
氷床が溶けたあとに大気中の二酸化炭素が炭素固定で減少した点からも、
一部の細菌が光合成で大量の酸素を作り出したのはありえそうですね。
全球凍結は英語でスノーボールアース(snow ball eath)とよばれ、
凍結というと怖いイメージがありますが、地球が凍ったことで生物は劇的な進化をとげ、
その後の人類の誕生につながったのかもしれません。

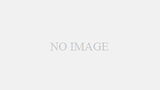
コメント