平均55.5点(前年比;-0.1点)

問題はこちら→東京都教育委員会
大問1(小問集合)-39.4%
(1)B…イ、C…エ、D…ウ、A…ア 29.4%!

*BEは線路の近く。
Bの次で線路の下を通る→Bでは目線の上に線路がある。イ
Eの次で線路の上を通る→Eでは目線の下に線路がある。ア
ウ:登り坂と丁字路がヒント。Dは丁字路である。
利根川の近くの水準点が7.8、Dの北側に23とあるので登り坂になる。
水準点は2022年都立大問1(1)で登場している。標高を求めるときの基準点。
エ:旧取手宿本陣表門は地図に記載がない!
ポイントは『直前の地点から約470m進んだこの地点』
前の地点から距離が500m弱なのはBC間だからC。
@余談@
取手宿は水戸街道の宿場(宿駅)の1つ。
本陣は大名や公家、幕府の役人など位の高い者が宿泊する施設。
脇本陣はそのサブ。庶民は基本的に旅籠に泊まった。
(2)エ 37.7%
*『戦国大名が領国を支配する目的で定めたもの』→戦国時代の分国法
領国…所有している国。領土・領地。
武田信玄の『甲州法度之次第』、今川義元の『今川仮名目録』など。
領国統治のための法で、喧嘩をした者は理由を問わず双方を罰する喧嘩両成敗の規定がよくみられる。
領国内での築城禁止や婚姻の許可制なども定められた。
ア:御成敗式目…貞永式目ともいう。鎌倉時代3代執権北条泰時。
初めての本格的な武家法で、のちの分国法や武家諸法度の基礎になった。
イ:大宝律令…701年(飛鳥時代末期)。唐の律令制を模範として文武天皇のときに制定。
律は刑法、令は行政法を示す。国体の基礎固めとして、天皇を中心とする中央集権国家の樹立を目指した。
律令を統治の基本とした国家を律令国家といい、中央政府には二官八省(二官=神祇官・太政官)が置かれた。
ウ:武家諸法度…江戸時代、2代徳川秀忠の名で出された大名を統制する武家法。
幕府の許可がない城の修理や築城、大名同士の婚姻を禁ずることで大名の強大化を防ぎ、幕藩体制を確立した。
起草者は家康に仕えた金地院崇伝。3代家光の改定で参勤交代が盛り込まれる。
(3)ウ 51.0%
*『衆議院議員総選挙後に召集』『内閣総理大臣の指名が行われる』→特別会(特別国会)
内閣が解散権行使→40日以内に総選挙→30日以内に特別会を召集する。
現実的には第一党の党首が内閣総理大臣(首相)に指名される。
参議院議員から指名してもよいが、これまでの首相はすべて衆議院議員から指名されている。
ア:常会(通常国会)…会期は150日(延長1回)1月中に召集され、6月中旬頃に閉会する。
1年中、国会が開かれているわけではない。次年度の予算や法律案についての審議が行われる。
イ:臨時会(臨時国会)…内閣の決定か、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求で召集される。
臨時会と特別会は延長が2回まで許される(常会の延長は1回まで)
エ:参議院の緊急集会…衆議院の解散で参議院は閉会となるが、内閣の求めに応じて開かれる。
大問2(世界地理)-44.6%
(1)C、イ 25.3%!
*A―バンコク(タイ)B―リヤド(サウジアラビア)
C―アディスアベバ(エチオピア)D―ワルシャワ(ポーランド)

雨温図から判定する。
ウ:降水量が少ない→乾燥帯(砂漠気候)のリヤド
エ:年中温暖・年降水量が多い→熱帯(サバナ気候)のバンコク
イ:比較的温暖で、エより気温が全体的に低い→高山気候(後述)のアディスアベバ
ア:比較的温暖・降水量が安定→温帯(西岸海洋性気候)のワルシャワ
西岸海洋性気候は暖流が運んできた暖気を偏西風が大陸に送ることで冬の厳しさが幾分和らぐが、
ワルシャワはやや内陸にあるため、1月の気温が氷点下と冷帯に近い。

高山気候はケッペンの気候区分にはないが、のちほど追加された気候。
年中温暖の熱帯は年較差(最暖月と最寒月の平均気温の差)が小さい。
一方、標高が高くなると100mごとに0.6℃下がるので(気温の逓減率)、
熱帯地域の標高が高い場所は、イの雨温図のように適度な温度で一定になる。
(エの気温の推移を下に平行移動した感じ)
エチオピアの首都アディスアベバは低緯度にありながらも標高の高いエチオピア高原にあり、
一年中過ごしやすい高山気候に分類される。

コーヒーの木になるコーヒーの実(果実)
エチオピアはコーヒーの名産地で、エチオピア高原南部のカッファ地方はコーヒーの原産地といわれている。年較差が少ないので季節変動の影響を受けにくく、また、標高が高いと日較差(1日の最高気温と最低気温の差)が大きいため、良質なコーヒー豆が育ちやすい。激しい寒暖差にさらされることでコーヒーの実が引き締まり、味が凝縮して美味しくなるからである。エチオピアや隣国のケニアではバラの生産が盛んである理由も同じで、大きくて張りのある花弁をもつ品質の良いバラが生育する。
(2)P…ア、Q…ウ、R…エ、S…イ 59.2%
*P―メキシコ、Q―フィジー(ポリネシア)、R―バングラデシュ、S―イタリア
三大穀物→米・小麦・とうもろこし
ア:『とうもろこしが主食、その粉から作った生地を焼き、具材を挟んだ料理』
→メキシコ料理のタコスなど。

タコスの皮である「トルティーヤ」はトウモロコシの粉から作られる。
イ:『沿岸部で柑橘類やオリーブの栽培』→地中海式農業の特産品→イタリア
地中海性気候は夏に亜熱帯高圧帯に覆われるため、少雨になる。
乾燥に強いオリーブやコルクガシといった硬葉樹林、柑橘類やブドウが栽培される。
温暖湿潤の冬季では小麦がつくられ、羊やヤギの移牧(季節で場所を変える牧畜)が行われる。
ウ:『さとうきび・バナナ』→熱帯性植物→南太平洋のフィジー
国土面積が小さい島国ゆえ、穀物全体の生産量は著しく少ない。
『バナナの葉に様々な食材とタロイモを包んで蒸した料理』→ロボという伝統料理があるようです。


南国フィジーで、のんびり退職生活より。
地面に穴を掘って焼き石を入れ、金網に乗せた食材をバナナの葉でフタをして蒸します。
アルミホイルで丸く包まれているのがタロイモです。
タロイモはやせ地でも栽培しやすく、アフリカでも食べられている。
エ:『稲作が行われ、米が主食』→モンスーンアジアのバングラデシュ
『河川が形成した低地』→ガンジスデルタ
バングラデシュ南部はガンジス川(国内ではパドマ川)の河口にある巨大な三角州地帯に位置する。
国土の半分以上が標高10mもなく、サイクロンの通り道でもあるため、高潮や洪水の危険度が高い。

グーグルマップより。バングラデシュの南東部はミャンマーに接し、それ以外はインドに囲まれている。
インドは茶の生産量2位。インド北東部のアッサム地方はアッサムティーで知られる茶の名産地。
このように考えれば、『バングラデシュの北東部で茶の栽培』もうなづける。

バングラデシュの農産物といえばジュートも有名。
ジュートとはシナノキ科の草の茎から採取する植物繊維で袋の素材になる。
近年は繊維・縫製産業も盛んで、日本で売られる服にMade in Bangladeshのタグを見かける。

『鶏やヤギの肉と共に牛乳から採れる油を使った米料理』→ビリヤニというそうです。
ジャンバラヤみたいで普通にうまそう。
(3)Z、ア 49.2%
*W―ウルグアイ、X―マレーシア、Y―南アフリカ共和国、Z―オランダ

Ⅱが判断しやすい。多くは近隣諸国との経済的な結びつきが強い。
ア:EU諸国で占められる(2020年にイギリスはEU離脱)→オランダ
EU圏内ではヒト・モノ・資本(カネ)・サービスの移動の自由(4つの自由)が保障されている。
オランダは酪農(チーズ)のイメージはあるが、なぜか豚肉が日本の輸入品目1位になっている…。
2019年の日本の輸入額が伸びたのは、日EU経済連携協定の発効が影響したのかもしれない。
イ:南米2ヵ国(ブラジル・アルゼンチン)、輸出額が最も低い→南米のウルグアイ
ブラジルと同様、牛肉の輸出が多い。ここ最近は中国との関係強化を図っている。
ウ:最もあてにくい。Ⅱで欧米が見られる。アフリカ最大の工業国である南アフリカ共和国。
エ:隣国のシンガポールからマレーシア。
マレーシアでは天然ゴムのプランテーション農業が広く行われていたが、
ゴムの木の老木化や合成ゴムの台頭からアブラヤシへの転作が進められた。
アブラヤシからとれる植物油(パーム油)は食品や石鹸、洗剤などの原料になる。

統計を頼りにしてもいいが最後のEUがわかりやすい。正答はオランダである。
ポルダーは6年前の都立大問6(1)で出題されている。
オランダの正式名称は『ネーデルラント王国』。ネーデルラントは低地を意味する。
国土の約4分の1はポルダーとよばれる干拓地でできている。ポルダーの土地利用は主に酪農。
干拓とは河川や海を堤防で仕切り、水を抜いて新たな陸地をつくること。

かつては排水の動力にオランダを象徴する風車が使われていた。
現在はポンプが使用され、風車は観光資源になっている。
また、オランダは都市への出荷を目的とする園芸農業が盛んで、
チューリップの球根や野菜を周辺のヨーロッパの都市に輸送している。
大問3(日本地理)-57.7%
(1)A…ウ、B…イ、C…ア、D…エ 68.9%
*A―秋田、B―静岡、C―奈良、D―鹿児島
ア:『南東部は季節風の影響から国内有数の多雨地域』『木材の生育に適し、古くから林業が営まれる』
→森林率(森林面積の割合)の高い奈良。
紀伊半島は季節風の影響から温暖かつ台風の通り道ゆえ降水量も多く、森林が育成しやすい。
『高品質な杉』→吉野杉

国土交通省より。前段は『紀の川』の説明である。
イ:『中西部の台地は明治時代以降に開拓、国内有数の茶の生産量』→静岡
茶の生産量1位:静岡、2位:鹿児島。静岡の茶畑といえば牧之原台地。
明治政府は失職した武士の救済策(士族授産)の一環として牧之原台地の開墾を奨励した。
『北側の3000m級の山々が連なる山脈』→赤石山脈(日本アルプスは北から飛騨・木曽・赤石)
『東部の半島』→伊豆半島。火山は熱海の温泉がイメージしやすいか。
伊豆半島は南にあった海底火山が火山島に成長し、プレートの動きに乗って日本列島に衝突してできた。
ウ:『稲作に適しており、銘柄米を生産』→あきたこまちの秋田
『夏に吹く北東の冷涼な風』→やませ
東北地方の太平洋側は夏にやませの影響で冷害や日照不足を引き起こす。

ジオテックより。前段の河川は米作りに欠かせない雄物川。
奥羽山脈と出羽山地のあいだにある横手盆地を貫流して秋田平野を形成する。
エ:『火山灰が積もってできた台地』→シラス台地が広がる鹿児島
水はけが良く、稲作には不向き。畜産や茶・さつまいもの栽培が行われている。
●飼育頭数ランキング●(2024年度)
肉用牛→1位:北海道、2位:鹿児島、3位:宮崎(乳用牛は1位:北海道、2位:栃木)
豚→1位:鹿児島、2位:北海道、3位:宮崎
採卵鶏→1位:千葉、2位:茨城、3位:鹿児島
ブロイラー(肉用鶏)→1位:鹿児島、2位:宮崎
『2つの半島に挟まれた湾の中に位置する島』→薩摩半島と大隅半島に挟まれた鹿児島湾にある桜島
『北東側の県境に位置する火山』→霧島山
鹿児島には種子島、屋久島、奄美群島など離島が多い。
(2)ア、W 30.9%!
*W―千葉、X―愛知、Y―兵庫、Z―広島

ア:決め手は他の都道府県への通勤通学者の多さ。郊外のベッドタウンである千葉。
人口は多いものの、県庁所在地の千葉市以外にも人口が分散している。
(東京に近い市川・船橋・浦安、常磐エリアの松戸・柏、人口増の流山、市原・八千代・習志野も多い)
京葉工業地域は化学工業の割合が高く、市原市に巨大な石油化学コンビナートがある。
イ:輸送用機械→自動車、オートバイなど。
エがトヨタの愛知とわかれば、2番目に割合が高いイはマツダのある広島。

府中町より。マツダの本社は広島市の中にある府中町にある!
広島東洋カープの本拠地はMAZDA Zoom–Zoomスタジアム。
広島市は山口寄りにあり、他県に通勤通学する県民は少ない。4県の中では最も人口が少ない。
ウ:おそらく最もわかりづらい。千葉に次いで周囲に通う人が多い兵庫。

国土地理院の地図を加工。人口の多い市が大阪に近い海岸線沿いに集中している。
関東に住んでいると出てきにくいが、神戸市以外に西宮、尼崎、明石、姫路などに人口が分散する。
神戸周辺では化学・製鉄・造船など多様な重化学工業が発達している。
エ:人口最多&製造品出荷額最高、輸送用機械が強い→トヨタのお膝元である愛知

Ⅰが分析できればⅡは即答できる。製鉄所は千葉市と君津市が有名。
京葉工業地域は京浜工業地帯からの分散を目的として戦後50年代から発展していった。
千葉県は都心に近い北西部または千葉市のある中央部に人口が集中する。
(3)例:自動車を使わずに公共の交通機関だけで日常生活に必要な機能を利用できる。 73.3%

*コンパクトシティに関する記述問題。
『将来の富山市における日常生活に必要な機能の利用について』
現状と比較し、自宅からの移動方法に着目して述べる。
日常生活に必要な機能の利用は注釈に書いてある。
現状は自動車を使わなければ利用できない機能があるが、
将来は自動車を使わず、公共の交通機関のみですべて利用できるようになっている。
@コンパクトシティ@
少子高齢化が著しい地方都市では、各所に空き地や空き家が増加して都市の密度が小さくなる「都市のスポンジ化」が進み、生活利便性の低下や行政サービスの非効率化、治安の悪化を招いている。コンパクトシティは町の中心部に住宅や都市機能を集積させることでスポンジの高密度化を図る。

コンパクトシティを実践した富山市では、日常生活に必要な市内の施設へ容易にアクセスできるように、LRT(ライトレール)という次世代型路面電車を走らせている。LRTは低床式ゆえ高齢者でも乗り降りがしやすく、自動車と比べて環境負荷が少ない。ヨーロッパの都市ではパークアンドライド(最寄りの駅で駐車(パーク)し、都市へは公共の交通機関にライドする)と結びついてLRTが普及している。
大問4(歴史)-39.7%
(1)エ→ア→イ→ウ 45.8%
*エ:遣隋使・大化の改新→飛鳥時代
645年、中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我氏を滅ぼす(乙巳の変)。孝徳天皇を擁立して中大兄皇子は皇太子となり、中臣鎌足を内臣に任命して国政の改革に乗り出した。一連の政治改革を大化の改新といい、我が国最初の元号である『大化』がつくられた。このとき、唐から帰国した僧の旻と高向玄理が国博士とよばれる政治顧問に就いた。
ア:最澄→平安時代
桓武天皇は仏教勢力を平城京に残すことで関係を断ち、新しい政治を立て直す目的で長岡京に遷都した。都の造営中に桓武天皇が信頼していた藤原種継が暗殺される。桓武天皇の弟である早良親王も事件の疑いをかけられ、彼は食事を断って無罪を主張したが亡くなってしまう。その後、桓武天皇の近親者がなくなり、自らも病に侵された。一連の原因は早良親王の怨霊にあるとおそれた桓武天皇は、794年、山背国(現在の京都府南部)に新たな都である平安京に遷都した。
最澄(伝教大師)は平安初期の僧。唐から帰国して比叡山延暦寺を立てて天台宗を広めた。
空海(弘法大師)は高野山金剛峰寺を立てて真言宗を広めた。
いずれも密教で、大日如来という仏を信仰対象として加持祈祷を重んじる仏教。教えの内容は部外者に非公開。

天台宗の総本山・比叡山延暦寺の根本中堂。国宝です。
延暦寺は「古都京都の文化財」として世界文化遺産に登録されている。
なぜ滋賀の大津にある延暦寺が古都京都なのか?
陰陽道で北東方向は鬼が出入りする不吉な方角とされる鬼門で、
鬼門除けのために平安京の北東にあたる比叡山に延暦寺を建てた。

同じく不吉とされる裏鬼門の南西には石清水八幡宮がある。
イ:執権→鎌倉時代
執権は将軍を補佐する役職。3代将軍源実朝の死後、執権の北条氏が実権を握っていく。旧仏教から弾圧を受けた栄西は鎌倉で臨済宗の布教に努めた。禅宗の考えは武士の気風と合い、臨済宗は鎌倉幕府の保護を受けて発展していく。2代将軍源頼家と北条政子は臨済宗に帰依し、頼家は栄西を開山(寺院を開いた初代住職)として京都に建仁寺を建立した。5代執権北条時頼は蘭渓道隆を開山として建長寺を、8代執権北条時宗は無学祖元を開山として円覚寺を鎌倉に建立した(建長寺と円覚寺は鎌倉五山の1つ)
ウ:勘合を用いた朝貢形式の貿易→勘合貿易(日明貿易)は室町時代
朝貢とは中国皇帝に使節を派遣して貢ぎ物を献上する代わりに、返礼品や位などを授かる外交形態。3代将軍足利義満と明の皇帝永楽帝とのあいだで形式的な朝貢が結ばれる。当時、明は倭寇対策のために自国民の出国や私貿易を禁じる海禁政策を行っていた。永楽帝(明の皇帝)は義満に倭寇の取り締まりを約束させて朝貢外交が始まる。日本は形式的に明の属国となり、足利義満には日本国王源道義の称号が与えられた。正式な貿易船と倭寇を区別するため、勘合とよばれる札を互いに折半・持参し、取引の際に照合した。
輸入品…銅銭(永楽通宝)、生糸、絹織物、陶磁器、書籍。
輸出品…銅、硫黄、刀剣、漆器。
(2)例:荒浜から太平洋を通る航路と、酒田から日本海を通って下関から瀬戸内海に入り、
大阪を経由し太平洋に出て江戸に向かう経路がある。
寄港地で物流の適正な管理が行われ、年貢米が江戸に輸送された。 39.6%

*問題文に挙げられた寄港地を結ぶと上図のようになる。
2つの航路を東廻り航路、西廻り航路という。
輸送経路と寄港地の役割に着目して年貢米の輸送について述べるが…問題として妙(;´・ω・)
公式解答によると、太平洋を通る経路と日本海+太平洋を通る経路とコンパクトにまとめている。
そのままだし、記述形式で出題するほど価値はあるのか。。
寄港地の役割は問題文の丸写しでOK。
@@
江戸時代では海上交通の整備がすすみ、舟運が活発に行われた。
航路の整備に尽力した河村瑞賢の名は覚えておこう。
東廻り航路も酒田を起点に北上して津軽海峡を通り、荒浜までいくルートが拡張された。
(3)A…ウ、B…エ、C…ア、D…イ 36.2%
*ウ:日米和親条約の締結(1854)
アメリカは対中貿易の足掛かりと北太平洋での捕鯨船の寄港地を得るために日本の開国を望んでいた。1853年、サスケハナ号に搭乗したマシュー・ペリー提督が浦賀に来航。フィルモア大統領の国書を提出して幕府に開国を迫った。翌1854年、日米和親条約を締結。下田と箱館(函館)を開港して、アメリカ船に薪、水、食糧の補給を行うようになる。同種の条約をロシア・イギリス・オランダとも結んだ。
エ:西南戦争(1877)
徴兵令、廃刀令、秩禄処分で特権を奪われた士族の明治政府に対する不満が高まる。明治六年の政変で征韓論を主張して要職を辞職した西郷隆盛を盟主として、1877年に大規模な不平士族の反乱が起きた(西南戦争)。熊本城の攻防戦から戦局が変わり、近代的な軍隊制度を整えていた政府軍が勝利。城山の戦い(鹿児島)では、軍楽隊が死にゆく西郷を悼む思いで演奏をしたという。西南戦争での敗北を機に不平士族は武力ではなく言論をもって政府に対抗するようになる。
ア:日英通商航海条約の調印(1894)
明治政府にとって不平等条約の改正は喫緊の課題であった。1886年、和歌山県沖で沈没したイギリス船ノルマントン号で日本人の乗客全員が水死した。このノルマントン号事件ではイギリス人の船長に無罪(のち3ヵ月の禁固)が言い渡され、国内世論で大きな反発を招いた。1894年、日清戦争開戦の直前に外務大臣陸奥宗光がイギリスと日英通商航海条約を結び、領事裁判権の撤廃に成功する。関税自主権の回復は1911年、小村寿太郎の日米通商航海条約で成就した。

イ:関東大震災(1923)
1923年9月1日正午前、マグニチュード7.9の巨大地震が関東を襲った。死者・行方不明者は10万人以上にのぼる。当時は木造の建築物が多かったため、家屋の倒壊だけでなく、火災による被害も大きかった。東京都墨田区の陸軍被服本廠跡(軍服の製造工場)では、台風による強風とともない炎が竜巻状になる火災旋風が起こり、避難していた被災者3万8千人が亡くなった。また、「朝鮮人が井戸に毒を投げた」といった震災デマが広がり、これを信じた民間の自警団が多数の朝鮮人を殺害した。

東京都より。東京市長を務めた後藤新平。
震災の翌日、内務大臣に就任して帝都の復興を目指した。
都市の区画を整理、昭和通りや靖国通りといった主要幹線道路の整備、
隅田公園など広い公園の設置は避難所や火除地の役割が期待された。
関東大震災に関する自然災害伝承碑は東京の各所に建てられている。
(4)A…ア、B…イ、C…エ、D…ウ 37.2%
*ア:サンフランシスコ平和条約の締結(1951)
吉田茂首相はサンフランシスコ講和会議に出席してサンフランシスコ平和条約に調印した。翌1952年の条約発効から連合国48ヵ国との間で日本は独立国としての主権を回復する。朝鮮の独立を承認、台湾・千島列島・南樺太の領有を放棄、琉球諸島(=沖縄など)や小笠原諸島についてはアメリカの信託統治の下に置かれた。
イ:エネルギー革命(1960年代)
戦後、基幹産業にヒトやモノを重点的に投資する産業復興政策(傾斜生産方式)のなかで石炭の増産が図られた。日本の高度経済成長期にあたる1960年代に主要エネルギー源が石炭から石油にシフトするエネルギー革命が起こる。①石油は重量あたりの発熱量が高く、②貯蔵や運搬が容易でタンカーやパイプラインで運べる。③天然ガスには劣るものの、石炭と比べると比較的有害物質の排出量が少ない。石炭の需要低下を受けて多くの炭鉱が閉山に追い込まれた。また、石油への転換は重化学工業の発展や自動車の大衆化(モータリゼーション)につながる。
エ:2度の石油危機(1973・79)
1973年、第四次中東戦争の勃発により、OPEC(石油輸出機構)が原油の供給制限と原油価格の引き上げ(3か月で約4倍の高騰)を行った(第1次オイルショック)。国内の重化学工業は大きな打撃を受け、石油関連製品の値上げは狂乱物価とよばれる著しいインフレを引き起こす。翌1974年には戦後初のマイナス成長を記録し、高度経済成長が終わりを告げた。1979年に起きた第二次オイルショックのきっかけはイラン革命。原油価格が3年間で3倍弱まで上がる。対米貿易摩擦の激化→1980年代
ウ:冷戦終結(1989)
冷戦は『ヤルタからマルタへ』。地中海に浮かぶマルタ島でアメリカのブッシュ大統領とソ連のゴルバチョフ共産党書記長が会談し、冷戦終結が宣言された(マルタ会談)。1990年、東西ドイツが統一。この年にゴルバチョフは東西冷戦を終結に向かわせた功労者としてノーベル平和賞を受賞する。翌1991年、超大国・ソビエト連邦が崩壊。盟主を失った陣営では「秩序」がなくなり、民族対立や地域紛争が再燃した。ユーゴスラビア内戦では大勢の難民が生まれた。
大問5(公民)-59.0%
(1)イ 85.5%
*憲法14条1項『すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、
社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない』
法の下の平等が明記されているので平等権と選びやすい。『社会的身分』は一時的ではなく、継続的に社会において占める地位。『門地』は家柄などを指す。
『平等』は各個人を一律に扱う絶対的平等ではなく、異なる事情があれば異なる扱いをしてもよい相対的平等を意味する。異なる扱いをすることに合理的な理由があれば平等権侵害にはならない。(高所得者と低所得者で税率が異なる累進課税は憲法違反にならない)
また、結果の平等(実質的平等)ではなく、機会の平等(形式的平等)を保障する。ゴールを同じにするのではなく、スタートラインを等しくて、その後の競争は個人の能力や努力に委ねる。実質的平等の保障は14条ではなく、「国家による人権」である社会権の保障で考慮される。
ア:『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する』
生存権。社会権の基礎的な人権で、1919年のワイマール憲法で初めて保障された。
ウ:『何人も、自己に不利益な供述を強要されない』
黙秘権(自己負罪拒否特権)。刑事責任を追及されるおそれのある供述を拒否できる。
エ:『何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない』
裁判を受ける権利。請求権の1つ。
@アファーマティブ・アクション@
差別を受けてきた人たちを優遇して格差の是正を図る措置を積極的差別是正措置(アファーマティブ・アクション、もしくはポジティブ・アクション)という。アメリカでは1960年代から導入され、就労や昇進、大学入学といった場面でマイノリティに属する人たちを積極的に受け入れた。なかでもクオータ制は一定の優遇枠(割り当て)を設ける制度で(とくに政治分野で使われる)、いくつかの国で採用されている。アファーマティブ・アクションはやり過ぎると逆差別を生む強力な副作用を含む点に注意が必要である。

男女共同参画局より。世界経済フォーラム(ダボス会議)が発表した日本のジェンダー・ギャップ指数は2024年度で146ヶ国中118位であった。健康と教育はハイスコアだが政治と経済、特に政治分野でのスコアが著しく低い。2024年11月11日基準で日本の国会議員における女性議員比率は19.0%。地方議員や首長ではさらに低い比率になっている。経済分野の女性管理職比率(課長級以上)も2023年度の厚労省調査によると12.7%しかない。
果たしてこれらの数値は性差による能力や適性に基づく結果なのだろうか。それを考慮しても国民の過半数もいる女性の比率としてはとても低いように思える。社会構造的にはびこる不利益的な差別があるのならば、永続的ではなく、一時的な経過措置としてアファーマティブ・アクションの意義はあるのかもしれない。もっとも、過大な優遇にならないよう期限や条件の設定には慎重な判断を要する。近年は女子枠を設ける日本の理系大学が増えている。
(2)C、ウ 29.0%!
*2019年都立大問5(3)では折れ線グラフで出題されている。

*概算で対処する。
2021年では、20兆/100兆≒約20%を超えた。
1989年では、20兆÷6≒3兆、3兆/60兆≒5%→C
@@
ウ:消費税は商品の販売やサービスの提供に対して課される税金で、税収が景気変動や人口構成の変化の影響を比較的受けにくく、安定的に徴税ができる。消費税は所得に関係なく負担の割合が等しいので、低所得者ほど負担が大きくなる(逆進性)。消費税は間接税の1つで、税金を負担する人(担税者)は買い手、税金を納める人(納税義務者)は売り手と異なる。地方自治体にも納付され、税率10%の場合は国の消費税が7.8%、地方消費税が2.2%に配分される。
1989年(平成元年)、竹下登内閣で消費税が導入された。当時の消費税率は3%だったが、1997年の橋本龍太郎内閣で5%、2014年の安倍晋三内閣で8%に引き上げられた。2019年の安倍内閣では原則10%としつつも、外食や酒類以外の食料品と週2回以上発行される新聞は軽減税率で8%に据え置きされている。
ア:歳入の不足分を賄うため、借金により調達される収入→公債金、将来世代に負担が先送りされる。
イ:給料や商売の利益などに課される→所得税。収入に応じて税率が高くなる(累進課税)
エ:法人の企業活動により得られる所得に対して課される→法人税
(3)エ 66.4%
*『地球上の「誰一人取り残さない」スローガン、17のゴールと169のターゲット、
持続可能でよりよい世界を目指し全ての国が取り組むべき国際目標』→持続可能な開発目標(SDGs)
SDGs=Sustainable Development Goals
2000-2015年の15年間で達成すべき国際目標MDGs(ミレニアム開発目標)に代わるものとして、2015年に開催された『持続可能な開発サミット』で2015-2030年の15年間で達成すべき国際目標SDGsが「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に取りまとめられた。

17の目標は覚える必要はないですが、一読はしておきましょう。
17の目標それぞれに細かい目標(ターゲット)が定められている。
MDGsは発展途上国の開発課題が中心であったが、SDGsは先進国も含めたすべての国を対象とする。
(4)例:有権者の範囲を拡大したり、成年年齢を引き下げることで、18歳から社会の構成員としての自覚を促し、若者が主体となって新しい国づくりを担うこと。 55.2%

*Ⅱの主な改正点に着目して、『国の若年者に対する期待』を述べる。
憲法改正の国民投票が20→18歳に引き下げ。
公職選挙法の改正により、選挙権年齢が20→18歳に引き下げ(有権者の範囲拡大)
民法の成年年齢も20→18歳に引き下げ。
18~19歳の者を大人として扱うことで『社会への参加時期を早める』
→大人としての自覚、主権者・社会の構成員としての自覚を促す。
『若年者が将来の国づくりの中心』となる国家として目指している。
以上の内容をまとめればいい。
@シルバー民主主義@
超高齢社会である日本は2024年の高齢者率が29.1%、2070年には40%ほどまで上昇するとの推定がでている。数の多い高齢者の政治的影響力が高まることをシルバー民主主義という。シルバー民主主義では高齢者の利益を優先する政策が行われやすくなり、反面、若者や子育て世代に向けた政策は滞るおそれがある。
総務省より、年代別投票率の推移。
令和3年度の10代投票率は42.23%、20代は36.50%しかないが、60代は71.38%、70代以上は61.90%と高い。若者が将来の国づくりの中心となる国家にするには、若者世代の投票率を上げることが急務である。シルバー民主主義の克服策として、日本維新の会の代表を務める吉村洋文氏が「0歳児選挙権」を提唱した。これは0歳児から選挙権を認め、親権者に子の選挙権の代理行使を許す制度。斬新でユニークな発想ではあるが、一人一票の原則(憲法14条1項、44条)に関する重大な例外を許容するので導入には慎重な議論を要する。
大問6(総合問題)-59.2%
(1)A…イ、B…ア、C…ウ、D…エ 47.3%
*A―ドイツ、B―フランス、C―イギリス、D―ガーナ
ア:『1789年に市民革命が起こる』→フランス革命
第三身分(平民)が三部会に代わる国民議会を設立、封建的な旧体制(アンシャン・レジーム)の打破を目指す。
1789年、絶対王政の象徴であったバスティーユ牢獄をパリ市民が襲撃して革命の火ぶたが切られた。

『モナ・リザ』『ミロのビーナス』『サモトラケのニケ』『民衆を導く自由の女神』
など世界的に有名な美術品を数多く所蔵するパリのルーブル美術館。
世界文化遺産。かつては王家の宮殿として使用されていた。
ガラスのピラミッドは美術館のメインエントランスになっている。


左が『湖畔』、右が『読書』
作者はヨーロッパ人のように思えるが、印象派の影響を受けた黒田清輝の作品。
17歳のときに法律家を志す目的でフランスに留学したが、芸術の道に傾倒するようになる。
イ:ロベルト・コッホはドイツの細菌学者。

コレラ菌や結核菌、炭疽菌を発見、結核菌の感染を確認するツベルクリン検査を編み出す。
コッホと関連してよく出てくる人物は、同じく細菌学者の北里柴三郎である。
コッホのもとで指導を受け、破傷風菌の純粋培養、血清療法の確立、ペスト菌の発見など数多くの功績を残す。
彼が所長を務める伝染病研究所からは野口英世や志賀潔(赤痢菌の発見)を輩出した。
『1871年に統一』→ドイツ帝国
鉄血政策(軍事力増強)を進めたビスマルクを首相とするプロイセン王国が小国に分立していたドイツを統一。
ヴィルヘルム1世を皇帝とするドイツ帝国が成立する。(ドイツ帝国は第1次世界大戦で崩壊)
森鴎外は『舞姫』の著者。東京帝国大学(現・東京大学)医学部を卒業した医者で軍医を務めていた。
ウ:『1902年に日本と同盟を結んだ』→日英同盟→イギリス
ロシアの南下政策に対抗するために日露戦争前の1902年に日英同盟を結ぶ。
(第1次世界大戦後のワシントン体制・四か国条約で日英同盟を破棄)
夏目漱石は東京帝国大学を卒業後、松山の中学で英語教師を勤めてからロンドンに留学した。
漱石がロンドンに行く道中で立ち寄った、1900年開催のパリ万博では動く歩道が展示されていた。
帰国してから『吾輩は猫である』『坊ちゃん』などの名作を表す。
シェイクスピアはイギリスの劇作家。四大悲劇→『ハムレット』『リア王』『マクベス』『オセロー』
エ:『熱帯地方』→ガーナ

国土地理院の地図を加工。ギニア湾の位置を確認。
カカオ豆生産量1位:コートジボワール、2位:ガーナ
野口英世は黄熱病の研究で知られる。幼少期に井戸に落ちて左手に火傷を負い、
百姓の仕事ができない代わりに学の道を志して医者になった。
伝染病研究所に入り、北里柴三郎のもとで細菌学を研究する。
多くの業績を残すが、最期は自身が研究していた黄熱病にかかり亡くなった。
(ちなみに千円札の肖像は夏目漱石→野口英世→北里柴三郎)
(2)ウ 63.5%
*『アメリカ合衆国に本社がある証券会社の経営破綻などを契機に発生した世界金融危機』
→リーマン・ショック(2008)
サブプライムローンとよばれる低所得者向けの住宅ローンの債権(銀行が貸したお金を返してもらう権利)を細かく分けて小口にした証券が様々な金融商品と組み合わせて販売された。格付け会社がその信用力に高いランク付けをしたこともあり、世界中の投資家たちが購入した。
やがて、アメリカ経済の景気が後退、金融の引き締めが強まって住宅価格が下がった。返済不能となった債務者(ローンの借り手、家の購入者)が続出、債権が焦げ付いて回収ができなくなると、サブプライムローン関連の証券を大量購入していたアメリカ大手の投資銀行リーマン・ブラザースが破産をする。2008年、これを皮切りに世界的な金融危機(リーマン・ショック)が発生した。世界同時不況の影響は日本にも及び、株価は軒並み大暴落する。リーマン・ショックによる深刻な金融危機に対処するため、ワシントンDCでG20サミットが開かれた。
(3)ア 66.7%
*『1945年、一部の国を除き他国の植民地とされていた』『民族分布を考慮しない直線的な境界線』
→アフリカ州
19c後半の帝国主義。資源の供給や市場の開拓、余剰資本の投下先を求めて、
イギリスやフランスをはじめとするヨーロッパの列強がアフリカ諸国を植民地支配する(アフリカ分割)

世界の歴史まっぷより、アフリカの植民地化地図。
エチオピアとリベリア以外はすべて植民地にされている。
イギリスはエジプトのカイロと南端のケープ植民地を結ぶ縦断政策、
フランスはアルジェリアからサハラ砂漠を南下、東のジブチを目指す横断政策をとった。
両国はスーダンのファショダで衝突、一触即発な状況に陥ったが(ファショダ事件)、
フランスが譲歩したことで両軍の激突は免れ、スーダンはイギリスの支配下にはいることになる。
アフリカの国境に直線が多いのは、支配者側が緯線や経線に基づいて勝手に引いたから。
民族分布を考慮せず、隣国で少数民族となった者たちが迫害を受けるなど現代の民族紛争の火種になる。

『1960年に多くの国が独立』『2020年は50ヵ国を超える加盟国』
60→65年の増加率が最も高く、2020年で50を超えるアがアフリカ州。
1960年の国連総会で「植民地と人民に独立を付与する宣言」が採択されたことで、
多くのアフリカ諸国が独立を果たした。1960年はアフリカの年とよばれている。
@@
他の選択肢を検討。
1945年時点の原加盟国と比べ、伸び率の高いイはアジア州。
アフリカ州と同様に独立後の加盟が目立つ。
1990→95年で急激に増えたウはヨーロッパ州。
1991年のソ連解体で衛星国であった東欧諸国が国連加盟を果たす。
最も原加盟国の多いエが南北アメリカ州。

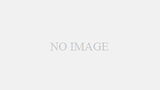
コメント